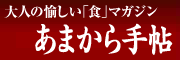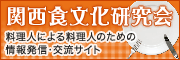« 「Tsukimi」 大阪・ウォルドーフ・アストリア大阪・寿司 | メイン | 「サケトコロ タナカ」 京都・室町仏光寺・居酒屋 »
2025年11月26日
「つつむ」 東京・新橋・奈良まほろば館
奈良の季節の食材、風土、歴史をお届けするイベント
「つつむ」が東京・新橋にある「奈良まほろば館」で開催された。
「つつむ」とは元来胎児を形どる文字であり、
いろいろなものを包み込むという意味も生まれた。
柿の葉茶でお出迎え。
まずはトークセッション。
川島宙さん 奈良の「アコル ドゥ」のオーナーシェフ
平井宗助さん 「平宗」(株)柿の葉寿司代表取締役
中谷圭祐さん 「ゐざさ」(株)中谷本舗常務取締役
それぞれが考える奈良の食文化、歴史などを語り
平井さんや中谷さんは柿の葉寿司の歴史や背景を語ってもらった。
中谷さんは、ルーツを再発見し、考える。
そんなテーマで3人の匠のトークセッションの後は食事となった。
最初は川島シェフの料理から
メニューには記載されていなかった一品
雲子のフリット
生地のサクふわ感が見事。
中身の濃密な白子にも感動。
心を奪われるスタート。
「熊野灘の鯖 炒り米と大和茶」
奈良にも熊野灘からの鯖街道がある。
その鯖を塩で締めて吉野に送ったことから奈良の柿の葉寿司が起こったと言われる。
塩で締めた鯖に春菊の水分と大和茶を寄せる。
適度な苦味と炒り米の粒々の食感も効果的であった。
「野迫川のトキシラズ 古代醤とオリーブ」
アマゴの雌雄。雌のことをトキシラズと呼ぶ。大ぶりのアマゴ
軽くスモークしたトキシラズに焼いた椎茸 そこに古代醤とオリーブオイルを合わせる。
泡は白味噌の発酵泡。その香りと薫香ある時知らずの出会いが素敵。
「白子のポチャール 生ハムのベール 柿の葉茶とシェリー トリュフ風味」
鱈はスペインでも食べられてきた食材。
もしその白子をスペインで食べる習慣があれば、ということを想像して作り上げた料理。
柿の葉茶の苦味と発酵した印象をトリュフの香り シェリービネガーはポン酢の役割。
生ハムのベールがアクセントを添える。
「自家製塩鱈と大和牛のタルタル 白菜漬けのクレマ」
塩鱈(バッカラ)・大和牛は柿の葉で包み火入れ、それぞれエスケシャーダとタルタルに。
キャベツは塩漬けで発酵のイメージ。そこに塩麹を使った大和橘香りも。
保存食しての柿の葉寿司を塩鱈に置き換えた一品。
次は「ゐざさ」にうつる

「杉の香りの『ゐざさ寿司』 大和橘とマス」
酢で漬け込んだマスに吉野杉の薫りをつけ 大和橘を混ぜ込んだシャリに合わせる。
このシャリが面白い。
「焼き鯖と海の香りの柿の葉寿司」
大和茶で炊き上げ、乾燥茶葉を混ぜ込んだシャリ、中にオリーブオイルやハーブで漬け込んだキュウリを挟む。脂の乗ったやや厚めの焼き鯖。この組み合わせの妙に感銘を受ける。
そして「平宗」へ
「秋の柿の葉すし 香りのベール 子持ち鮎 宇陀牛蒡」
柿の葉寿司は柿の葉の香りが定番。
ここでは柿の葉茶とコーヒーの香りを纏わせる。
子持ち鮎は柿の葉茶のほうじ茶で柔らかく炊き上げ甘露煮に。香りのベールは柿の葉茶で。一方宇陀牛蒡は甘辛く炊き上げコーヒーの香りをつける。シャリには柿酢を使う。このコーヒーのインパクトは強く、途中でオリーブオイルと塩をつけると味わいの印象が変わる。


奈良の伝統を尊びながら、次世代へ向けてのメッセージが詰まったイベントであった。
新たな柿の葉寿司にも川島シェフのアイディアが光っていた。
奈良まほろば館
東京都港区新橋1‐8-4 SMBC新橋ビル1F・2F
03-6263-9656
Web連載「amakara.jp」=====
門上武司のグルメ旅「皿までひとっとび」
★門上武司の旅vol.12:一汁一菜と酒肴で新たな“昼風”を吹かせる岡山市『あまおと』
★門上武司の旅vol.13: 地元の幸と旨い肉で最良のひと皿に。岡山市『ラボッカ』
YouTubeチャンネル「Round Table」=====
森 義文(カハラ・オーナーシェフ)
森 義文(part1) – YouTube
兼井俊生(手打ち蕎麦 かね井・店主)
兼井俊生(part1) – YouTube
堀木 エリ子(和紙作家、堀木エリ子&アソシエイツ代表)
堀木 エリ子(part 1) – YouTube
西田 稔(Bar K6 / cave de K / Bar kellerオーナー)
西田 稔(part 1) – YouTube
======協力:株式会社マイコンシェルジュ
投稿者 geode : 10:00